ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事4)
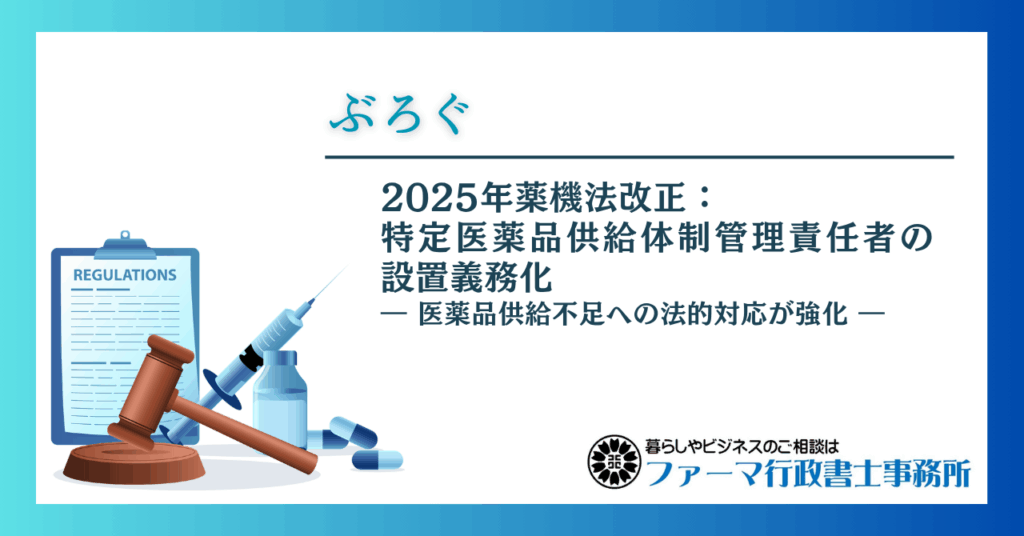
2025年の薬機法改正の重要な柱の一つが、「医薬品の安定供給体制の強化」です。
この改正では、「特定医薬品供給体制管理責任者」という新たな責任者制度が創設されました。これは、ここ数年社会問題化している「医薬品供給不足」への法的対応として注目されています。
⚠️ 背景:相次ぐ医薬品供給不足と社会的影響
近年、製薬企業の不正製造や出荷停止などが相次ぎ、抗菌薬や解熱鎮痛薬など、日常診療で欠かせない医薬品が全国的に不足する事態が続いています。一つの企業の不祥事や原薬の供給途絶が、全国の医療現場に連鎖的な影響を及ぼす――そんな構造的リスクが明らかになりました。
このような中、「医薬品の安定供給を企業任せにせず、法的に支える仕組みが必要」との認識から、今回の改正が行われました。
🏛 改正のポイント
① 「特定医薬品」の概念を新設
改正薬機法では、従来の医薬品分類に新たに「特定医薬品」という概念が設けられました。これは、供給不足が生じた場合に社会的な影響が大きい医薬品を対象とするものです。
具体的には、次のいずれにも該当しない医薬品が「特定医薬品」とされます。
- 要指導医薬品
- 一般用医薬品(OTC医薬品)
- 薬局が自らの設備で製造し、その場で販売・授与する医薬品(体外診断用医薬品を除く)
- その他、製造販売・販売状況を把握する必要がないものとして厚生労働省令で定める医薬品
つまり、「医療現場で使用される医療用医薬品の大部分」がこの対象となります。
この分類により、国が社会的に重要な医薬品の供給状況をより的確に監視できるようになります。
② 「特定医薬品供給体制管理責任者」の設置を義務化
特定医薬品を製造販売する業者は、特定医薬品供給体制管理責任者を置かなければなりません。
この責任者は、次のような役割を担います。
- 医薬品供給計画の策定・管理
- 製造委託先や原薬メーカーとの連絡・調整
- 供給に支障が生じるおそれがある場合の早期報告
- 行政機関との情報共有
これにより、供給体制の監視と責任の所在が明確化され、法的に一元管理される体制が整います。
③ 「供給管理」を企業内部統制の一部に
この新制度は、品質保証や安全管理と並び、供給管理を企業の内部統制に位置づけるものです。
これまで供給体制は企業の自主的取り組みに委ねられていましたが、改正により、法令で定める体制整備・記録保存・権限付与などが義務化されました。
厚生労働省令で、責任者の権限・資格要件・業務記録の方法などが今後具体的に定められる予定です。
💬 これまでと何が違うのか
従来、供給問題は「行政指導」にとどまり、法的な義務や罰則を伴う仕組みは存在しませんでした。
改正後は、供給体制の構築やモニタリングを怠った場合、行政処分や業務改善命令の対象となる可能性があります。
これにより、“品質・安全管理”から“品質・安全・供給管理”へと法の射程が拡大しました。
🌱 今後の実務への影響
- 製造販売業者は、自社の供給リスクを体系的に把握し、リスクマップを作成する必要があります。
- 委託製造や輸入を行う場合は、海外サプライチェーンも含めた情報管理体制が求められます。
- 責任者は、社内で十分な権限を持ち、経営層と直接やり取りできる立場でなければなりません。
✨ まとめ
今回の改正は、「供給不足の再発を防ぐための仕組みづくり」を法的に位置づけた点で画期的です。
これにより、国民が必要な医薬品を安定的に入手できる体制の実現が期待されます。
今後、関連する省令やガイドラインが順次示される見込みです。
製薬企業・流通業者・医療機関は、法施行スケジュールを踏まえた実務対応の準備が必要です。
📌 ファーマ行政書士事務所では、薬機法改正対応や供給体制に関する法令対応についてのご相談を承っています。
※本記事は、2025年5月21日に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)の内容及びそれによって予測される影響について記述しています。法解釈を含む内容については、個別の事案やその後の解釈等により異なる場合があります。正確な情報は必ずご自身でご確認いただくようお願いいたします。
投稿者プロフィール

-
1987年塩野義製薬株式会社に入社。2011年まで中央研究所にて、感染症領域および癌・疼痛領域の創薬研究に従事。その間、1992年には、新規β-ラクタム系抗菌薬の創製で博士(薬学)を取得。
1998年から1年間、米国スクリプス研究所に留学。帰国後、分子標的抗がん薬の探索プロジェクトやオピオイド副作用緩和薬の探索プロジェクトを牽引し、開発候補品を創製。2011年10月、シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社に異動となり、新規に創設された化学支援部門を担当し、軌道に乗せる。2013年には塩野義製薬株式会社医薬研究本部に戻り、外部委託管理、契約相談、化学物質管理などの研究支援業務を担当。2020年から3年間、創薬化学研究所のラボマネージャーとして、前記研究支援業務を含む各種ラボマネジメントを担当。2023年3月に定年退職。
2023年4月に、薬事・化学物質管理コンサルティングを行う行政書士として、ファーマ行政書士事務所を開業し、現在に至る。
最新の投稿
 ブログ2026年1月19日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事16)
ブログ2026年1月19日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事16) ブログ2026年1月12日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事15)
ブログ2026年1月12日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事15) ブログ2026年1月5日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事14)
ブログ2026年1月5日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事14) ブログ2025年12月27日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事13)
ブログ2025年12月27日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事13)

