ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事1)
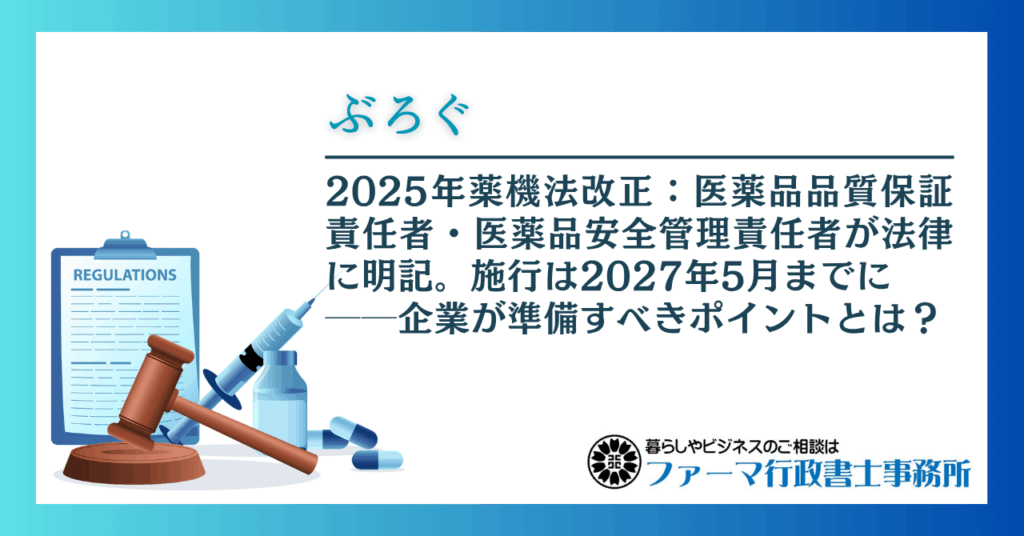
はじめに
2025年5月に公布された薬機法改正(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律)では、製薬関連企業に大きな影響を与える見直しが行われました。
その中でも注目すべき改正点の一つが、「医薬品品質保証責任者」および「医薬品安全管理責任者」の設置義務が法律に明記されたことです。
これまでこれらの責任者は厚生労働省令により定められていましたが、今回の改正で法令上の位置づけが格上げされました。
この改正は、単なる形式変更ではなく、企業における品質と安全の両面からの管理体制を強化するものです。
改正の概要と施行時期
改正法は2025年5月21日に公布され、施行日は公布から2年以内(最遅で2027年5月20日まで)とされています。
現時点(2025年10月)では具体的な施行日は未定ですが、遅くとも2027年春までには完全施行される見込みです。
従来、省令に基づき「医薬品品質保証責任者」および「医薬品安全管理責任者」の配置が求められていました。
しかし、省令は法律の委任を受けて定められる技術的ルールであり、法的拘束力はあるものの、企業の現場では運用の幅があると受け止められることもありました。
今回のように薬機法本文に「医薬品品質保証責任者」「医薬品安全管理責任者」が明記されたことで、
- 義務の法的重みが明確化
- 行政による監督・指導の根拠が強化
- 経営層の責任もより明示化
といった実務的な変化が生じます。
法制化の背景と目的
背景には、医薬品の品質と安全性をめぐる課題の複雑化があります。
製造委託や海外製造所の増加、グローバルなサプライチェーンの拡大などにより、品質保証・安全管理の双方で専門的かつ独立した責任体制が求められるようになりました。
このため、製造・出荷前の品質保証を統括する「医薬品品質保証責任者」と、製造販売後(市販後)の安全性情報を統括する「医薬品安全管理責任者」の二つの役職を法律上明確に位置づける必要が生じました。
これにより、品質と安全の両領域における責任体制が整理され、より実効的な品質・安全確保の仕組みが制度的に担保されることになります。
省令と法律の違い──何が変わるのか
省令:行政機関(今回のケースでは厚生労働省)が定める詳細ルールで、技術的・運用的事項を規定。
法律:国会で制定される基本原則。違反は即「法律違反」として行政処分・刑事罰の対象となる。
これまでも省令に基づく義務違反は処分の対象でしたが、法律に明記されたことで、
- 経営層の法的責任がより明確化
- 行政の監督権限が直接化
- 責任者の社内での位置づけが強化
という実質的な変化が生じます。
すなわち、形式的に責任者を置くだけでは不十分であり、実際に権限を行使し、機能する体制を整えることが法的に求められるようになります。
実務現場への影響
医薬品品質保証責任者と医薬品安全管理責任者の役割分担
- 医薬品品質保証責任者:製造・出荷・品質管理などの全工程を統括し、製造販売承認品の品質を確保する。
- 医薬品安全管理責任者:製造販売後の副作用・感染症等の安全性情報を収集・評価し、必要な措置を講じる。
両者が連携し、製品のライフサイクル全体を通じて品質と安全を確保する体制が求められます。
人材・組織体制の整備
これらの責任者には、それぞれの分野での専門知識と実務経験が必要です。
組織図や職務分掌を見直し、責任者の権限・報告経路・意思決定プロセスを明文化することが重要です。
内部統制と監査の強化
行政による査察では、責任者が単に配置されているだけでなく、実際に機能しているかどうかが問われます。
内部監査・報告記録の整備、経営層への定期報告体制の構築など、運用の実効性を高める必要があります。
施行までに企業が準備すべきこと
- 人材の要件確認と育成
- 医薬品品質保証責任者・医薬品安全管理責任者の候補者が法の要件を満たすか確認し、必要に応じて教育・研修を実施する。
- 社内規程・職務分掌の見直し
- 両責任者の職務・権限を明文化し、総括製造販売責任者との関係を明確化する。
- 監査・記録体制の整備
- 内部監査やリスク報告、是正措置の記録を体系化し、経営層による確認プロセスを明確化する。
まとめ
2025年薬機法改正により、「医薬品品質保証責任者」と「医薬品安全管理責任者」の設置義務が法律に明記されました。
従来は省令で定められていたものが法制化されたことで、企業の品質・安全管理体制は経営層が主体的に関与すべき課題へと位置づけが変わりました。
施行は公布から2年以内(最遅で2027年5月20日まで)。
人材確保や体制整備には時間を要するため、今の段階から計画的に準備を進めることが求められます。
ファーマ行政書士事務所では、薬機法改正に伴う組織体制の見直しや社内規程の整備支援を行っています。
品質保証・安全管理体制の整備をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は、2025年5月21日に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)の内容及びそれによって予測される影響について記述しています。法解釈を含む内容については、個別の事案やその後の解釈等により異なる場合があります。正確な情報は必ずご自身でご確認いただくようお願いいたします。
投稿者プロフィール

-
1987年塩野義製薬株式会社に入社。2011年まで中央研究所にて、感染症領域および癌・疼痛領域の創薬研究に従事。その間、1992年には、新規β-ラクタム系抗菌薬の創製で博士(薬学)を取得。
1998年から1年間、米国スクリプス研究所に留学。帰国後、分子標的抗がん薬の探索プロジェクトやオピオイド副作用緩和薬の探索プロジェクトを牽引し、開発候補品を創製。2011年10月、シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社に異動となり、新規に創設された化学支援部門を担当し、軌道に乗せる。2013年には塩野義製薬株式会社医薬研究本部に戻り、外部委託管理、契約相談、化学物質管理などの研究支援業務を担当。2020年から3年間、創薬化学研究所のラボマネージャーとして、前記研究支援業務を含む各種ラボマネジメントを担当。2023年3月に定年退職。
2023年4月に、薬事・化学物質管理コンサルティングを行う行政書士として、ファーマ行政書士事務所を開業し、現在に至る。
最新の投稿
 ブログ2026年1月19日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事16)
ブログ2026年1月19日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事16) ブログ2026年1月12日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事15)
ブログ2026年1月12日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事15) ブログ2026年1月5日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事14)
ブログ2026年1月5日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事14) ブログ2025年12月27日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事13)
ブログ2025年12月27日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事13)

