ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事3)
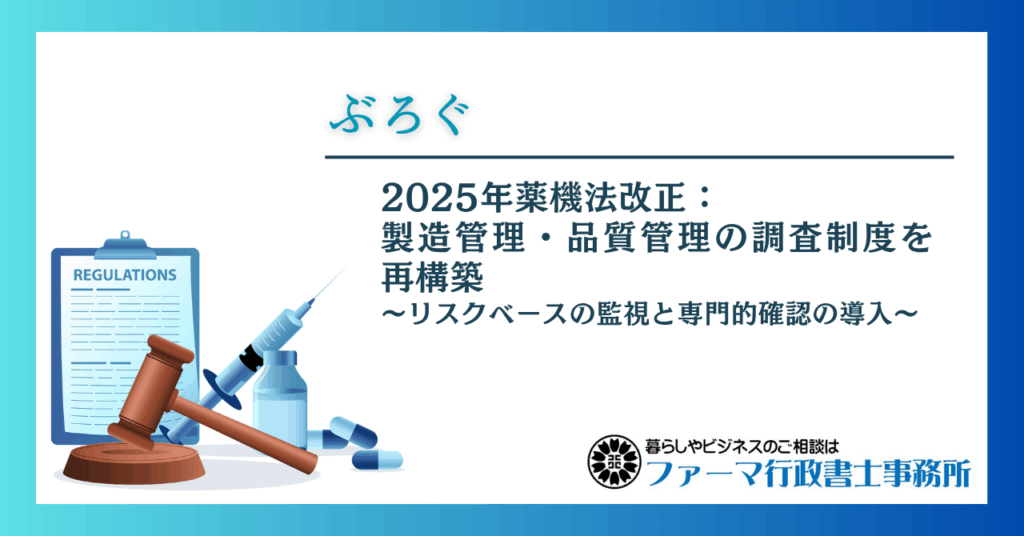
はじめに
2025年5月に公布された薬機法改正では、製造管理および品質管理に関する監督制度が大きく見直されました。
改正の柱は、
- 第14条第7項:低リスク製造所への調査省略制度の創設
- 第14条の2第3項:基準確認制度における専門的事項の確認義務の追加
の2点です。
これらの改正は、行政による監視を「一律」から「リスクに応じた重点管理」へと進化させるものであり、企業の品質保証体制にも新たな対応が求められます。
1.改正の背景
医薬品の品質不正やデータ改ざんなどの事案を契機に、製造現場への信頼確保が重要視される一方、適正に管理されている製造所にまで同頻度で調査を行うことの非効率さが課題となっていました。
また、製造工程そのものに高度な専門性を要する製品群(バイオ医薬品、再生医療等製品など)が増加したことにより、従来の一律調査では、品質の適正性を十分に把握できない場面も増えています。
こうした状況を踏まえ、改正では、「低リスクの製造所は調査を合理化し、高リスク・高難度の工程は行政による専門的確認を強化する」というリスクベースの監督体制が導入されました。
2.第14条第7項の新設:低リスク製造所の調査省略制度
第14条第7項の新設により、厚生労働大臣は、承認を受けた医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業者について、承認後3年以上ごとに行う製造所調査のうち、「製造管理または品質管理の方法が基準に適合していないおそれが少ない」と評価される場合、その回の調査を省略できることになりました。
この仕組みにより、過去の調査実績や自己点検の信頼性が高い製造所は、行政調査の頻度を減らせる可能性があります。一方、行政側としては、調査資源を重点リスク領域に再配分できるため、行政効率化の効果が期待されます。
実務への影響
この調査省略制度の導入により、企業側には新たな課題が生じます。
製造所が低リスク製造所としての調査省略を受けるためには、
- 自己点検結果・是正報告書などの記録を体系的に保管していること
- 過去の指摘事項への対応状況を明確に説明できること
- 品質保証体制が自律的に運用されていること
などが前提になると考えられます。
言い換えれば、調査省略は、企業自身が“調査不要と判断されるだけの信頼性”を積み上げる仕組みと言えます。これにより、品質保証部門・製造部門・薬事部門の情報共有体制を再点検することが、今後の重要課題となります。
3.第14条の2の改正:「専門的確認」の導入
第14条の2では、製造業者が厚生労働大臣に対して「基準適合性の確認」を求めることができると定められています。
今回の改正では、その制度の中に、「特に専門的知識を要する事項」に関する確認の義務が新たに組み込まれました。
製造工程が「医薬品の製造管理または品質管理に関して特に注意が必要な区分」に該当する場合、確認を求めようとする者は、厚生労働省令で定める「特に専門的知識を要する事項」について、厚生労働大臣に対して当該事項に係る確認を求めなければならない。
すなわち、基準確認制度の中に、高度な製造工程に関する義務的な確認申請の仕組みが新たに追加された形です。
「特に注意が必要な区分」「特に専門的知識を要する事項」とは
現時点(2025年10月)では、「特に注意が必要な区分」および「特に専門的知識を要する事項」は、いずれも厚生労働省令で定めることとされており、具体的な内容はまだ明らかになっていません。
制度趣旨からすれば、
- 無菌製剤や細胞培養工程など、高度な製造管理を要する区分
- 複雑な分析・評価を伴う品質管理手法
などが想定されますが、最終的な定義は今後の省令で確定する予定です。
実務への影響
この改正により、製造業者は次の対応を求められます。
- 工程ごとのリスク区分の把握:自社工程が省令で定める区分に該当するかを確認。
- 技術資料の整備:専門的事項に関する確認申請に必要なデータ・文書の整理。
- 部門横断的な準備体制:品質保証部門・薬事部門・技術部門の連携強化。
とくに「確認を求めなければならない」とされた場合には、申請手続に必要な資料の正確性と一貫性が、行政評価の鍵を握ります。
4.施行時期と今後の対応
これらの改正は、いずれも公布から2年以内(最遅で2027年5月20日まで)に施行される予定です。厚労省令による詳細(該当区分・専門的事項・手続要件)は、施行に向けて段階的に公表される見込みです。
企業は、今から以下の準備を進めておくことが望まれます。
- 自社の品質管理記録・自己点検結果の整理
- リスク分類を想定した内部評価体制の整備
- 行政確認・調査対応方針の再構築
まとめ
2025年薬機法改正は、製造管理・品質管理体制を「一律監査からリスクベースの重点監視へ」と進化させるものです。
- 第14条第7項:低リスク製造所への調査省略制度(行政・企業双方の効率化)
- 第14条の2第3項:専門的事項に関する確認義務(高リスク工程への重点確認)
この二つの制度改正に共通するのは、「品質管理体制の自律性と説明責任」が問われる時代に移行したという点です。
行政が“信頼できる体制”と判断できるかどうか。
その答えは、企業の日常的な運用・記録・改善の積み重ねにあります。
📌 ファーマ行政書士事務所では、薬機法改正対応に向けた製造管理・品質保証体制の整備支援を行っています。基準確認制度やリスク区分対応、省令施行への準備などについてもご相談ください。
※本記事は、2025年5月21日に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)の内容及びそれによって予測される影響について記述しています。法解釈を含む内容については、個別の事案やその後の解釈等により異なる場合があります。正確な情報は必ずご自身でご確認いただくようお願いいたします。
投稿者プロフィール

-
1987年塩野義製薬株式会社に入社。2011年まで中央研究所にて、感染症領域および癌・疼痛領域の創薬研究に従事。その間、1992年には、新規β-ラクタム系抗菌薬の創製で博士(薬学)を取得。
1998年から1年間、米国スクリプス研究所に留学。帰国後、分子標的抗がん薬の探索プロジェクトやオピオイド副作用緩和薬の探索プロジェクトを牽引し、開発候補品を創製。2011年10月、シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社に異動となり、新規に創設された化学支援部門を担当し、軌道に乗せる。2013年には塩野義製薬株式会社医薬研究本部に戻り、外部委託管理、契約相談、化学物質管理などの研究支援業務を担当。2020年から3年間、創薬化学研究所のラボマネージャーとして、前記研究支援業務を含む各種ラボマネジメントを担当。2023年3月に定年退職。
2023年4月に、薬事・化学物質管理コンサルティングを行う行政書士として、ファーマ行政書士事務所を開業し、現在に至る。
最新の投稿
 ブログ2025年12月15日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事12)
ブログ2025年12月15日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事12) ブログ2025年12月8日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事11)
ブログ2025年12月8日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事11) ブログ2025年12月1日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事10)
ブログ2025年12月1日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事10) ブログ2025年11月25日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事9)
ブログ2025年11月25日ファーマ行政書士事務所ブログ(薬事9)

